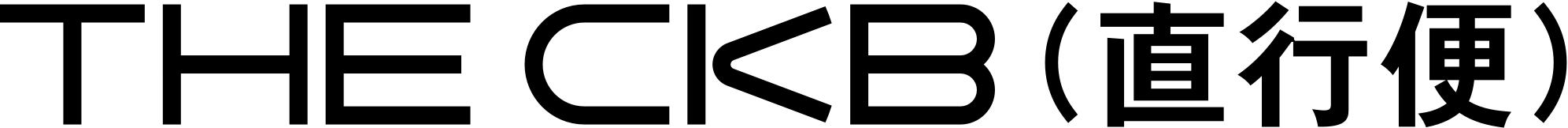大好評につき再開!国際送料0円
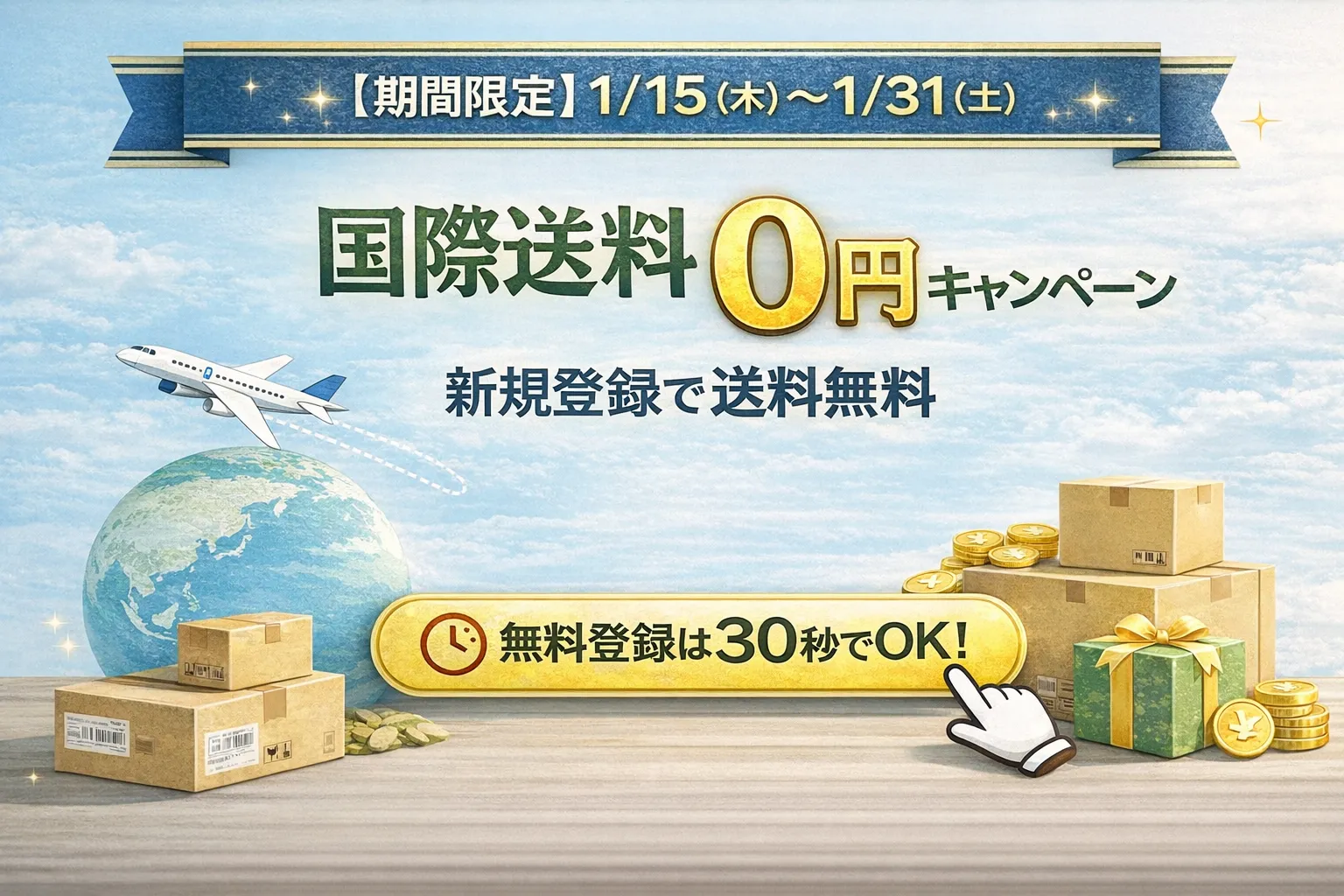
\ 海外調達・OEM・卸仕入れなら、THE CKB /
期間限定で「国際送料0円キャンペーン」を開催中です!
1月15日(木)〜1月31日(土)まで。
海外仕入れの負担を一気に下げて、 テスト販売も即スタートできます。
THE CKBは、小ロット仕入れからOEM・ODMまで、
あなたのビジネスを全力でサポートします。

越境EC事業者の皆様、消費税の「課税仕入れ」について正しく理解していますか?
この概念は、消費税の納税額を計算する上で非常に重要であり、インボイス制度の導入によりその重要性はさらに増しています。
本記事では、課税仕入れの基本的な定義から、非課税仕入れとの違い、さらには越境ECにおける非課税条件まで、幅広く解説いたします。
適切な知識を身につけ、消費税の適正な処理と節税に役立てましょう。

事業活動において発生する様々な取引の中で、消費税が課税される「仕入れ」を正確に把握することは、消費税の納税額計算の出発点となります。
ここでは、課税仕入れの基本的な意味とその仕組みについて詳しく見ていきましょう。
課税仕入れとは、事業者が事業のために他の事業者から課税資産の譲渡等を受けることを指します。
消費税法第2条第1項第12号において定義されており、事業者が商品やサービスを購入する際に支払った消費税のことを意味しています。
課税仕入れの要件は、以下の通りです。
消費税法上、この課税仕入れは仕入税額控除の基礎となる重要な概念で、事業者の消費税負担を軽減する役割を果たしています。
適切な理解により、事業者は消費税制度を有効活用することができるのです。
課税売上とは、事業者が商品やサービスを販売する際に顧客から受け取る消費税を含む売上のことです。
課税仕入れと課税売上は、消費税の計算において密接な関係があり、この両者の差額が事業者の実際の消費税負担額となります。
仕入税額控除については下表の計算例で確かめてください。
| 項目 | 金額 | 消費税額 |
|---|---|---|
| 商品仕入(課税仕入れ) | 100,000円 | 10,000円 |
| 商品販売(課税売上) | 120,000円 | 12,000円 |
| 納付税額 | ー | 2,000円 |
この制度により、消費税の重複課税を防ぎ、最終消費者のみが税負担をする仕組みが確保されています。
ただし、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)などの要件を満たす必要があります。

2023年10月から導入されたインボイス制度は、課税仕入れの取り扱いに大きな変化をもたらしました。
適格請求書発行事業者から受け取った適格請求書(インボイス)がある場合のみ、原則として仕入税額控除が可能となったのです。
インボイスの記載要件は以下の通りです。
免税事業者からの仕入れについては、経過措置として2026年9月まで80%、2029年9月まで50%の控除が認められていますが、段階的に控除割合は減少します。
このため、事業者は取引先の登録状況を確認し、適切な請求書の受領・保存を行うことが必要不可欠となっています。
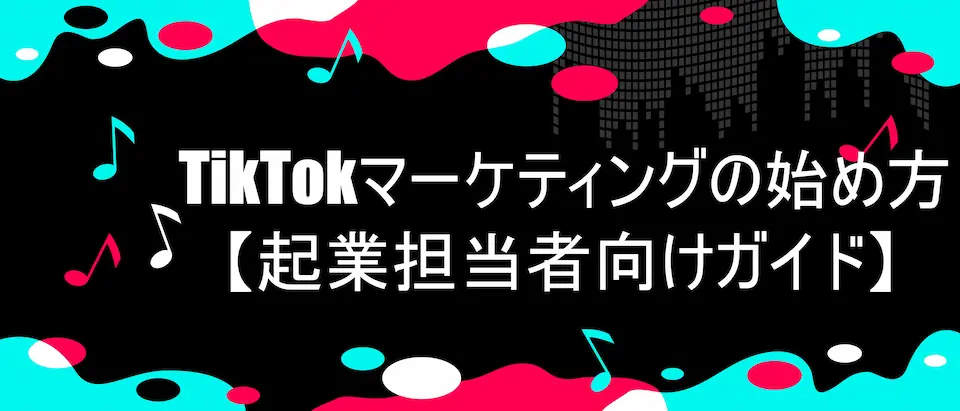
課税仕入れと非課税仕入れの区別は、消費税の計算において極めて重要です。
この区別を間違えると、仕入税額控除の適用誤りや税務調査での指摘につながる可能性があります。
業種や取引内容によって判断が分かれるケースも多く、実務上の注意点を理解することが必要です。
課税仕入れに該当する代表的な取引として、商品の仕入れが挙げられ、小売業であれば卸売業者からの商品購入、製造業であれば原材料の調達などが該当します。
これらの取引では、仕入先から適格請求書を受け取ることで、仕入税額控除の適用が可能となります。
課税仕入れの主な取引例は以下の通りです。
外注費についても課税仕入れの対象となりますが、外注先が個人事業主の場合、適格請求書発行事業者の登録を受けているかどうかの確認が必要です。
事業活動に必要な支出の多くが課税仕入れに該当し、適切な管理により税負担の軽減を図ることができます。
非課税仕入れは、消費税法で定められた特定の取引において、消費税が課されない仕入れのことです。
これらの取引では仕入税額控除の適用はできませんが、消費税の負担もないため、実質的な税負担への影響はありません。
非課税仕入れの主な取引例は以下の通りです。
代表的なものとして住宅用建物の家賃があります。
事務所として使用する場合は課税対象ですが、社員寮や社宅として使用する住宅部分の家賃は非課税となります。
金融取引や教育関連の支出についても、多くが非課税取引に該当するため注意が必要です。
業種によって課税仕入れの判断が複雑になるケースがあります。
実務上よく問題となる業種別のポイントを整理することで、適切な処理を行うことができます。
業種別判断のポイントは、下表を参照ください。
| 業種 | 課税仕入れ | 注意すべき非課税・免罪取引 |
|---|---|---|
| 建設業 | 建築工事、建設資材、下請外注費 | 土地造成工事の一部、重機リース(契約内容次第) |
| 小売業 | 商品仕入れ、店舗家賃 | 従業員社宅の住宅部分、免罪店向け酒類 |
| 飲食業 | 食材仕入れ、店舗設備 | 従業員福利厚生の食事代(要件次第) |
| サービス業 | システム利用料、ソフトライセンス | 海外からのサービス提供(国外取引) |
| 製造業 | 原材料、製造設備、外注加工費 | 輸出向け製品の関連費用(輸出免税適用時) |
建設業では、建物の建築工事は課税仕入れですが、土地の造成工事のうち土地の譲渡に該当する部分は非課税となるケースがあります。
小売業では商品の仕入れは基本的に課税仕入れですが、酒類の仕入れで免税店向けの場合は輸出免税の適用を検討できます。
サービス業では、海外からのサービス提供の場合は国外取引として非課税となる可能性があり、慎重な判断が求められます。
これらの違いを正確に理解し、適切な処理を行うことが必要なのです。

越境ECビジネスでは、国内取引とは異なる消費税の取り扱いが適用されます。
輸出取引や国外取引の特例により、課税仕入れが非課税扱いとなるケースがあり、事業者にとって税負担軽減の機会となります。
これらの制度を適切に活用するためには、要件や手続きを正確に理解することが重要です。
輸出取引における課税仕入れの非課税扱いは、輸出免税制度の一環として設けられています。
商品を海外に輸出する場合、その売上は消費税が免税となりますが、輸出のために行った課税仕入れについても特別な取り扱いが適用されます。
輸出免税適用の要件と対象は、下表を参考にしてください。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 証明書類の保存 | 輸出申告書、船荷証券、航空貨物運送状など |
| 直接関連性 | 輸出される商品に直接関連する課税仕入れ |
| 対象となる費用 | 梱包材料、輸送費、保険料、プラットフォーム手数料 |
| 対象外の費用 | 一般管理費的性格の強い支出 |
この制度が適用されるためには、まず輸出の事実を証明する書類の保存が必要です。
また、輸出される商品に直接関連する課税仕入れであることが要件となります。
越境ECプラットフォームを利用する場合、プラットフォーム手数料や決済手数料についても輸出に直接関連するものであれば対象となり得ます。
適切な書類整備により、輸出事業者の税負担軽減を図ることができます。
デジタルサービスの提供など、無形のサービスについても国外取引として非課税扱いとなるケースがあります。
これは「国外取引」の概念に基づくもので、サービスの提供場所が国外であると判定される場合に適用されます。
国外取引の判定基準は以下の通りです。
対象サービス例としては、以下のようなものが挙げられます。
越境ECでデジタルコンテンツを販売する場合、購入者の所在地により課税・非課税の判定が行われます。
国外取引に該当する場合、売上は非課税となりますが、そのために行った課税仕入れについては仕入税額控除を受けることができ、結果として事業者の税負担が軽減されることになります。

少額輸入免税制度は、一定金額以下の輸入品について消費税等を免除する制度です。
課税価格が1万円以下の貨物については、原則として消費税及び地方消費税が免除されます。
この制度は越境ECで海外から商品を仕入れる事業者にとって、仕入コストの削減につながる重要な制度です。
少額輸入免税制度の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免税基準 | 課税価格1万円以下 |
| 課税価格の算定 | CIF: 商品価格+運送費+保険料+諸掛り |
| 注意事項 | 意図的な分割は認められない |
| 合算ルール | 同一差出人・同一名宛人・同日の貨物は合計する |
制度の適用を受けるためには、まず課税価格の計算方法を理解する必要があります。
商品を複数回に分けて輸入する場合、意図的に1万円以下となるよう分割することは認められていません。
また、同一差出人から同一名宛人に送付される貨物が同じ日に複数ある場合は、それらを合計して判定されます。
越境ECビジネスでは、この制度を活用することで小口の商品仕入れにおけるコスト削減が可能となりますが、制度の趣旨を踏まえた適切な利用が求められます。
尚、関税の計算方法に関しては、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参照ください。

課税仕入れについて、多くの事業者が疑問に感じるポイントをFAQ形式でまとめました。
これらの質問を通じて、課税仕入れに関する理解をさらに深めていきましょう。
課税仕入と課税売上は、以下の通り消費税計算における表裏の関係にあります。
課税仕入:事業者が他の事業者から商品やサービスを購入する際に支払う消費税を含む取引
課税売上:事業者が顧客に商品やサービスを販売する際に受け取る消費税を含む取引
課税仕入れと課税売上の違いを、分かりやすく表にまとめましたので参照ください。
| 項目 | 課税仕入 | 課税売上 |
|---|---|---|
| 取引の方向 | 購入(支払う側) | 販売(受け取る側) |
| 消費税の扱い | 仕入税額工場の対象 | 納税義務の発生 |
| 事業者への影響 | 税負担を軽減 | 税負担を発生 |
| 計算例 | 11万円で購入→消費税1万円控除 | 13万円で販売→消費税3万円納税 |
消費税の計算では、課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除し、差額を納税することになります。
両者の適切な区分と管理により、正確な消費税計算が可能となり、過大納税や過少納税を防ぐことができます。
インボイス制度の導入により、免税事業者からの仕入れについては特別な取り扱いが設けられています。
免税事業者は適格請求書を発行できないため、原則として仕入税額控除を受けることができませんが、経過措置として以下のような段階的な控除が認められています。
・免税事業者からの仕入れに関する経過措置
| 期間 | 控除割合 | 必要手続き |
|---|---|---|
| 2023年10月~2026年9月 | 80% | 帳簿に「80%控除対象」記載 |
| 2026年10月~2029年9月 | 50% | 帳簿に「50%控除対象」記載 |
| 2029年10月以降 | 0% | 控除不可 |
経過措置の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が必要です。
帳簿には控除割合を明記し、適切な区分管理を行う必要があります。
免税事業者との取引継続を検討する場合は、価格交渉や契約条件の見直しなど、総合的な判断が求められます。
原則として、適格請求書(インボイス)がない場合は仕入税額控除を受けることができませんが、一定の取引については例外的に仕入税額控除が認められています。
これらは「適格請求書の交付義務が免除される取引」として定められており、帳簿のみの保存で控除が可能です。
インボイス交付義務免除取引の例は以下の通りです。
これらの例外に該当する場合でも、適切な帳簿記載が必要であり、取引の内容や相手方の氏名、取引年月日、対価の額などを明確に記録する必要があります。
例外規定の適用は限定的であるため、可能な限り適格請求書の受領を心がけることが重要です。
越境ECビジネスでは、輸出免税制度や国外取引の非課税規定を活用することで、課税仕入れに係る税負担を軽減できるケースがあります。
最も代表的なのは、海外への商品輸出における輸出免税の適用です。
越境ECでの課税仕入れ節約方法は下表の通りです。
| 方法 | 適用条件 | 節約効果 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 輸出免税 | 海外への商品輸出 | 売上免税+仕入控除 | 輸出許可書・船荷証券 |
| 国外取引 | 海外へのサービス提供 | 売上非課税+仕入控除 | 顧客所在地証明書類 |
| 少額免税 | 1万円以下の輸入 | 輸入時の消費税免税 | 特になし |
| プラットフォーム費用 | 輸出関連の手数料 | 仕入税額控除 | 請求書・利用明細 |
デジタルコンテンツやオンラインサービスの提供についても、提供先が海外の場合は国外取引として非課税扱いとなる可能性があります。
越境ECプラットフォームの利用料や国際配送料についても、輸出に直接関連する費用として仕入税額控除の対象となります。
ただし、これらの制度を適用するためには、適切な証明書類の保存や要件の充足が不可欠です。
課税仕入れは消費税制度の根幹をなす重要な概念であり、事業者が支払った消費税を仕入税額控除として活用するための基礎となります。
インボイス制度の導入により取り扱いがより厳格になった現在、適格請求書の受領と保存が原則として必要となっています。
特に越境ECビジネスにおいては、輸出免税制度や国外取引の非課税規定を適切に活用することで大幅な税負担軽減が可能です。
課税仕入れの適切な理解と管理により、事業者は消費税負担の最適化を図ることができます。
特に越境ECビジネスでは、国際取引特有の制度を活用することで競争力の向上につなげることが可能となるでしょう。

THE CKBへのお問い合わせ
ご契約・協業・法人様
03-4446-7313
受付時間 平日:10:00~13:00,14:15~19:00
LINEで相談してみる
受付時間 平日:10:00~13:00,14:15~19:00